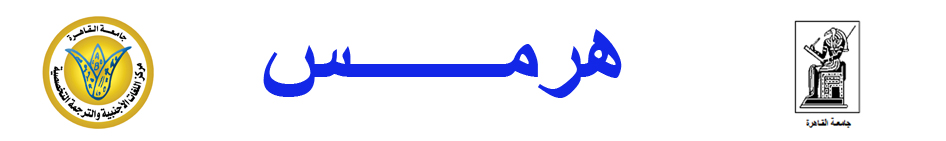
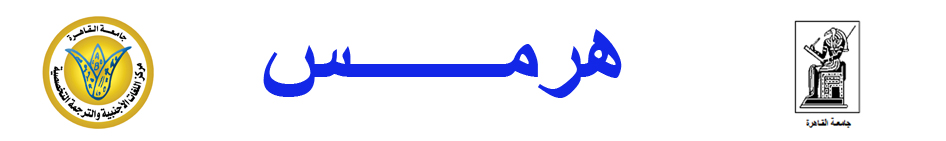
نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
Cairo University
المستخلص
1883年4月に5日間にわたり、大肢の外国人居留地で『日本において、キリスト教への信仰をはばむ仏教の宗教的な影響力』という宣教師の会議が開かれた (1) 。その会議では、神道と儒教についてはほとんど触れられておらず、日本でキリスト教の伝道・布教を妨げるのは仏教であると発表された。また同会では、欧米の有識者が来日し日本各地でキリスト教信道、教育、福祉、医療と看護などの活動に従事するキリスト教宣教師が集まっていた。かれらの活動は、近代的な知識や技術を用いるという方法が採用されており、明治初期の日本政府が指向していた近代化政策の一翼を担うという側面があった。日本におけるキリスト教に関する会議の第一日目に,伝道活動をさまたげる障害について論ずることは非常に妥当なことである(2)。
この会議には二種の受け止め方があり、多数の日本の知識人がヨーロッパの様々な事物を受け取り、拡大するようにすすめる一方、日本の旧来の文化と伝統を保護しなくてはならないと危機意識を抱き衝撃を受けた一部の知識人もいた(3)。その後者の内、井上円了(1858-1919)は日本の伝統としての仏教を再考察することを通じて、近代日本の公認教として仏教を保護しようと考えた。キリスト教に関する井上円了の批判を取り扱った貴重な論文や資料などがあり、哲学における仏教を再考察する円了の努力を取り上げた重要な研究もある。本稿では、いまだ十分に扱われておらず、触れられていない、円了が公認教を設けることで外国の宗教が起こす害を防ぎ、旧来の宗教を保護しようとした点に焦点に当てて、日本独自の宗教における仏教の位置づけを明らかにする。
本稿の流れは次のようである。第1章では、円了が『日本の政教論』を執筆する際に、どのような歴史的な背景があったかを参照する。第2章では、円了はどのように日本の旧来宗教を定義し、なぜ優先的に仏教を特待すべきであると考えているかを考察する。第3章では、円了が論じる、国体と政体における宗教の役目について解説する。また、同点において彼が考える、欧米の宗教と日本の宗教の特徴的相違を参照する。第4章では、円了が想定する、旧来の宗教を保護する方法、及び特待法を明確にしつつ、外国の宗教が導入される際にどのような恐れを考えているかを検討する。
第1章:歴史的背景
明治維新直後において、日本の仏教に大きな影響を与えた「廃仏殿釈」の運動は、見過すことができない事件であるといわれている。明治維新とは、王政復古を新政権の基盤として、徳川政権下の政治的・社会的秩序などすべての旧習を破壊すべきという考え方が誕生し、日本は外来の宗教である仏教を廃して、旧来の神道に復帰するべきであるという考え方が明治初期に非常に激しく興った。結果として、神仏の分離が行われ、このため地方によっては寺院、仏具の破壊や、僧侶、尼僧の還俗が強制されたので、伝統的な仏教がかなり壊滅的な打撃を受けたことは否定できない(4)。
その後「神仏判然令」が布達され、仏教と神道が日本の旧来の宗教であり、外来の宗教の影響を排除することが主旨となった(5)。しかし明治政府は、天皇制の基盤として、神道を中心にした国学の思想体系によって日本国を規定し、日本の特殊的な近代化を目指している。これに伴って発生したのがいわゆる「廃佛毀釈」である(6)。その「廃佛毀釈」と称される事態の以前には、仏教教団は存在していず、あくまで「ほとけ」に対する信仰とその信仰を共有する集団の存在しかなかった(7)。であるのに政府が仏教と神道を分離した理由は、多くの民衆の間では神も仏も信仰の対象としての違いがほとんどなかったためである。既成の仏教系信仰者集団がとった対策の中で最も早かったのは真宗の東西本願寺の動きであった。金策に苦しむ明治政府に資金の貸し付けを申し出て発言力を維持しようとしたのである(8)。一方明治政府の方では反仏教的な処置に対する農民を中心とした強い抗議運動に苦慮し解決策を見いだすことを模索していた(9)。
1872年に、明治政府は「教部省」を設置し、神社や寺院の建設や廃止の権限を置き管理責任を与え、さらに大教院を設置し教導職には神主のみでなく僧侶も任用されたのである。また、旧来の僧侶集団の一部は西欧への使節団や留学生を送り、近代化の手本たる欧米での宗教事情を見極めることで仏教を救おうとしたのである。言い換えると、みずからのあり方を「仏教」という近代的宗教のひとつとして確立していこうとしたのである(10)。また、島地黙雷や岩倉具視などは西欧視察の後に数々の建白書や論文を出した。その運動は実を結び宗教の自由を求める声は徐々に大きくなって、1875年5 月には大教院を解散し、1875年11月明治政府は「信教の自由保障の口達」で仏教徒の要求を認め信教の自由を保障した。さらに1877年10月には教部省を廃止したのである。仏教徒にとっては安堵するところではあったが、ところがその結果こんどはキリスト教の宣教師の数が急激に増えて仏教界はキリスト教への反対運動に力を注ぐことになる。その運動に大きな力を果たしたのは大谷派の教校出身で東京大学に進んだ井上円了(1858-1919)である(11)。
井上円了は『真理金針』や『仏教活論』等を著し、仏教とキリスト教とを比較して仏教の理論性を主張している。『真理金針』は1882年の出版であるが、元となった論考は『明教新誌』という仏教新聞に連載されたものである(12)。この当時円了はまだ20歳代の哲学青年であった。この井上の論旨は反キリスト教としてのみではなく、従来の仏教のあり方への厳しい批判もあり反省を促すものであった。彼にとっての仏教はあくまで学理に適合する宗教であり、そこには近代的な仏教学や西欧流の自然科学の知識による裏付けが存在していたのである。井上円了は1887年に現在の東洋大学の前身となる哲学館を創設する(13)。
また、憲法が発布された1889年前後から、「公認教制」の導入が議論され始め、宗教法案が貴族院に否決されるまでの約10年もの間、その論争が続いたのである。「耶蘇教」への批判は、少なくとも幕末期から仏教者における主要な課題であり、「切支丹禁制」の高札が撤去された1871年以降も、彼らはキリスト教が日本列島に流入する危険性について注意を喚起し続けた。しかし、1880年代以降「西洋」の学問や法的体系が日本に導入されるにつれて、それまでに展開されていたような「排耶論」が変化することとなる。1881年には国会開設が宣布されると、「国家の元」を図るための「宗教」に関する議論が高まり、またそれは明治政府が「不平等条約」の改正を目指して各国公使とのより積極的な交渉に取り組み、その実現に際して「内地雑居」なども避けられない事実として認識されるようになった時期でもあった。1892から1893年の議会において、内地雑居をめぐる議論がさらに展開すると、外国人の権利としての「信教の自由」も以前よりもまして問題視され、宗教法案の必要性も指摘されるに至った、1899年にキリスト教と神道、仏教の三つの「宗教」に関する53か条の法案が貴族院に提出されたが、仏教界のほとんどはキリスト教と共通の法案によって規制されることを批判し、反発する (14) 。仏教界の取り組みの結果、1900年宗教法案は貴族院において否決された。しかし同年に第二次山県内閣はそれまでの「社寺局」を神社局と宗教局に分け、多くの単発法令によって「宗教」を規定していくにつれ、仏教公認運動はほとんど消滅することとなる。この運動の内容は、柏原祐泉などの先学者によって「徳川封建治下における幕藩体制下の仏教の在り方と全く一致するもの」であり、「思想史的にみるならば、決して近代的な思想的基盤に立つものでない」と厳しく批判されたものである(15)。
次に教育の面における歴史的な背景を見てみよう。ここでは、谷川穣氏の「明治中期における仏教と俗人の教育」を参考にする(16)。谷川穣氏は、同稿において教育勅語が発布される1890年前後、いわゆる明治中期を対象に、近代また仏教者による俗人日本社会の形成における教育と仏教の関係をめぐる議論、教育的活動の実相を考察している(17)。明治初期に新政府が企図した神仏合同の民衆教化政策は学校教育振興と種々の摩擦をおこしつつ、頓挫する。その時、教導職、即ち教化者が補せられる役職が中心的な問題であった。以前の教育活動を実際に行っていたのは僧侶や神職(祠官・祠掌)らであった。明治維新後、彼らは地域にて学校教員として役割が期待されていたが、1873年には文部省によって「教育と宗教の分離」理念に基づき兼務を禁じられた。しかし実際は地域の期待を背景に各地において教員が不足していたため、各地で兼務が黙認されていた。1879年に、そうした状況の中で、教導職の教員兼務が事実追認的に解禁された。これを契機に、僧侶や地方官吏の一部から兼務を正当化し、一層進むべきであるという議論が仏教界に流行し、しばしば仏教的雑誌などに登場した(18)。
1875年には、こうした神仏合同教化の政策がとどまり、仏教の各宗派は近代的な教団形成に向け組織再編に乗り出し、そうした仏教界の動きは自宗派僧侶の養成に関心を向けるばかりであった。また、学校教育は「排仏的」存在として忌避される傾きが強く、仏教の復興及び布教と、学校教育とを対抗的関係とする観点が形成されていた。そこで、教導職の教化活動やその後の近代的な教団形成は、俗人子弟への教育という社会的機能(たとえば手習塾の師匠)を前代まで果たしていた仏教に、教育との分離を促した(19)。
第2章:旧来の宗教と歴史的縁故
本章では、円了はどのように日本の宗教を分別したのか、またなぜ旧来の宗教、とりわけ仏教を特待すべきと考えたのかを考察する。円了は『日本の政教論』の第三章から五章にわたり、日本の旧来の宗教と歴史上の縁故について解説している。
(20)
上述の文章は、円了が、日本旧来の宗教(神道、儒教、仏教)と外国からの新しい宗教を比較して、その利害を紹介しながら、文明の精神について説明しているものである。円了の考えでは、仏教は日本の宗教の中で、独特な特徴があり、日本文明の象徴であることを説得しようとしている。彼は、儒教には宗教の組織がない事から宗教としての体をなさず、また、仏教はインド伝来の宗教であるとは言え、日本の仏教はインドのそれとは異なることと、神道が日本在来の宗教であることから、長い時代において神仏二教が日本において認識されている宗教と成ったと主張している。さらに、仏教が日本に入って以来、一千数百年の間に数多くの改良を受け、社会の文物と相互に混同し、一種固有の日本性の仏教となったと強調している(21)。それ故、神仏二教は日本の純然で固有の宗教であるので、「これをヤソ教各派の今日わが国にあるものに比すれば、その等差同日の論にあらざるなり。」と強調している。
また、多数の例を取り上げて、神仏二教は日本史にて最も縁故ある宗教であることを検証している。そこで円了は欧米諸国を巡遊し、その国体と宗教との関係に関して見聞したことを使用して日本の伝統的な宗教を保護するように論じている。彼は、欧米諸国では各国の伝統が歴史上に積み重なっており、古来の宗教が保護されているという。ここで円了は、イギリスの歴史にて縁故があるキリスト教の例を挙げて関連性を主張している。彼は、「カンタベリー、ヨーク等は歴史上縁故ある寺院なるをもって、これを今日に保存し、これを今日に特待するなり」と述べている(22)。要するに、日本で従来の伝統と宗教を保護することは不思議なことではないと関連付けている。換言すれば、西洋諸国では歴史的な縁故がある宗教が優先されていると同じく、日本では国皇室国体の永続を保護するため、歴史的な縁故の深い宗教を保護し、その宗教を特待すべきであると強調している(23)。
さらに円了は、神道は日本史とのむすびを証明する必要がないという。一方、仏教も古来の本寺本山と僧位僧官は勅命勅旨によって設置されたものであり、日本の各地に寺院が創立され、住職が任命されたものであると弁証している。そして、彼らは国家鎮護に力を尽くし、「名実ともに仏教をもって国教に組織したるものなり」と述べている(24)。また、円了は「皇室歴朝の葬祭は仏教によりて営みしもの、および皇族にして仏門に帰し仏寺に入りしもの幾人あるを知らず、また勅命によりて寺院を封じ寺格を授けたるもの幾寺あるを知らず。」と解説している。彼によれば、日本の皇室と国体が永続するため、道理上また実際上ともにこうした歴史的な縁故を保護することが必要であると主張している。もしその縁故が排除された場合、日本の歴史的な事実が消され、皇室国体の永続は困難となると懸念している(25)。一方、外国の宗教は日本に全く縁故がない宗教なので、同様な特待をされるべきではないと主張している。
このように、円了は、日本の文明、とりわけ宗教文化は神道と、儒教、仏教という「三道の混和化合」より成り、この絆を分解すると日本文明の精神と文化の性質の基盤がなくなると考えている。また、彼によれば、日本風は外国と異なることや、日本人の特殊な精神は外国人と相違すること、日本国家という独立的存在、開国以来日本国と皇室が永続することなどは、すべてこの三道の混和化合の結果と影響にあるに違いないと強調している。従って、日本人心を維持し、日本独立を保存するため、旧来の宗教を永続させるべきであると述べている。円了は、旧来文化の中「かつ中古わが国の文学は全く仏教によりて成り、その時代の著書一として仏教の主義に出でざるはなし。その他、当時の美術、遊興、風俗、礼式、みな仏意に基づきて組織したるものなり。」と述べている(26)。こうした日本の独特的な風俗や、礼式、社会の秩序を守り、一国の独立を保つべきであると強調している。ここで、彼は以上の理論を検証するため、イギリスやフランス、ドイツなどの欧米諸国からの例を次々あげている。彼は、これらの国々が本をただせば同じ文明から派生したものだとしても、国家においても、人民においても相違があるので、各国がそれらの特徴的な違いを独立・保護しており、それが各国特有の性質となり優先されていると述べている。これと同様にすれば、日本の文明の源泉と精神を守ることを通じて日本の独立を永く維持することができるという(27)。ここで円了の指している日本の精神というのは、日本の風俗、礼式等の古来民間に伝来されたものであると定義するが、末に宗教と限定している。
以上のように、円了は日本の宗教と欧米諸国との比較をしばしば行っているが、彼は実際にどのように西洋諸国の現状を知り、それらの社会に浸透している文明の精神を認識しているかは疑問である。
第3章:国体と政体における宗教の役目
本章では、円了が欧米で見聞した宗教とその国々の国体との関係を明らかにする。また、円了が考える欧米と日本の宗教と国体、及び政治体制の相違を参照する。
3-1.円了における宗教と国体のむすび
円了は、日本及び西洋諸国における宗教と国体の関係、及び日本の宗教の独自性に関して以下のように述べている。
(28)
以上のように、円了は、欧米で触れた政教、所謂宗教と国体の関係を参考にしつつ、熱心に日本人に新知識を啓蒙することを志している。とりわけ、欧米で見聞した国体と歴史的縁故のある宗教との関連性を紹介している。これらの国々では各国その政治国体に最も相応しい宗教が優先され公認教とされている。一方、日本の土壌に根ざした仏教は、皇室国体の下に千年以上流布し、漸々改良発達して日本国体に最も適切な形質を取り、皇室を千数百年間永続するに最も力ある宗教であると主張している。従って、日本は欧米諸国、そしてそれらの国体と異なり、日本社会と国体に最適な宗教を公認教とすべきだと強調している。
また円了は、欧米諸国の事情を参考にして解説している。これらの国々は、各国は自分の政治国体に最も適切な宗教を優先し特待するという。つまり、これらの国々では、公認教または国教が定められる際に、その宗教は政体に害を及ぼさずに国体を安定させることが基準であると考えている。従って、日本も欧米の例と同様に、独立的な国体また政治体制に適合し、外国の宗教と異なる宗教を採用すべきであると主張している。円了の見解では、日本に存在している宗教の中で、旧来の宗教の他に日本の国体に適切な宗教は無いことが明らかであるという。そのため、日本でも日本の政治国体に支えを提供する宗教を特待し公認教とする必要があると強調している。
『日本の政教論』の「第七段 内国宗教間の調和」では、円了は同国にて相違の宗教間の調和が可能かどうかを論じている。彼は、欧米諸国からの例を挙げて、日本でも可能であることを解説している。彼の考えでは、あらゆる社会において様々な宗教があり、時代によって争いが生じる。ここで、相違の宗教の争いが同国の人心を離散させ、政治上の不幸不利になることを解説している。例えば、宗教間の不和で政治上の不和が生じ、また宗教上の争乱で政治上の争乱が発生すること、欧州史ではそのような例が乏しくないと論じている(29)。こうした争いが生じる時に、国体の崩壊の恐れがあり、実に国家の不幸となると懸念している。
日本の場合では、宗教間に生じる争いまた競争に関する円了の評価は次のようである。日本の宗教は、数世間の競争淘汰により、神道と仏教互いに相和する習慣ができ、両教が並存し並行し、不和争乱が起きる憂いがなく、神道と仏教は相互に相調和するものであるという。円了の考えでは、日本の宗教間の平和の理由は宗教家と政治家がこの調和に注意し、「政治上にて種々の方法を政教の間に施し、宗教内にて種々の解釈を宗意の上に下し、その極ここに 至るなり。」と述べている。しかし、外国の宗教のような信仰は「今日今時に入りたるものなれば、その性質といいその組織といい、我が従来の宗教と調和することあたわざるは必然なり。」と述べている(30)。ここで円了は、外教と日本の宗教の間の争いが生じるのみならず、外教間にも争いが生じ、また各派の間に不和争乱が起きるは必然となると論じている。
3-2.円了における宗教と政体
円了は、欧米諸国では様々な宗教と宗派があると同時に、多様な政治体制があることについて以下のように論じている。
(31)
ここで彼は、欧米各国が異なった宗教を有する例として、ロシアはギリシア教を用い、ドイツはルーテル宗を用い、イギリスはエピスコパル宗を用い、アメリカは独立宗を用いていると述べている。円了は、こうした多種多様な相違は、これらの国々で採用されている政治体制の違いから生じると考えている。また、各国が採用する政体は旧来の伝統と宗教との調和を考慮されているという。例えば、共和政治の下にはその政治と同一の組織を有する宗教があり、君主政治の下にはその政治と同一の性質を有する宗教があるという例を挙げている。また、ローマ宗とギリシア宗、エピスコパル宗はみな君主国に適合する宗教であり、独立宗と会議宗は共和国に適切な宗教であると解説している。また、独立宗と会議宗がアメリカで流行しているのはその組織と共和政体に最も適するからであるという例も挙げている。円了は、欧米諸国の例を踏まえたうえで、日本でも最も適切な宗教を採用するようにすすめている。彼によれば、神道と仏教は明確に日本の宗教であるという。仏教について、「付法伝灯、血脈相承を重んずること各宗派みなしからざるなく、はなはだしきは世系、法脈ともに連綿たるの宗派あるに至れるは、けだしわが国体、古来皇統一系をもって建てたるによるや疑いをいれず。」と述べている。
続いて、「かつわが国の各宗各派はみな管長を設け教正を置きて末寺末徒を統轄するがごときは、ローマ宗、エピスコパル宗等と同組織を有するものにして、」と述べ、これらの宗教と宗派は日本の政体に最も適切なものであると指摘している。であるのにもかかわらず、円了によれば、欧州諸国の国々の宗教が日本に入ったとしたら日本の国体に少なくとも害があると述べている。さらに、共和政体に基づくアメリカの宗教は君主国に不適切であるので、日本の皇統一系国に適合する宗教ではないと指摘している。それは、その宗教の組織は自由や共和、平権同等の主義に基づいているものなので、その宗教上の思想は日本の政体上の思想と対立することは当然であると強調している。そのため、円了は、「わが国にあるヤソ教会はアメリカより入るもの最も多きは、我が輩今より、その他日に生ずる利害いかんを憂慮するところなり。」と警告している。
第4章:円了の恐れ
本章では、円了がどのように日本の固有文化を保護し維持しようとしているかを考察する。また、彼はどのように外国の宗教を考え、そしてどのような危険を警告しているかを明らかにする。
4-1.日本の精神が西洋化される恐れ
西洋文明の導入に伴い流入する外国の宗教が、日本人の愛国心を弱め、更には日本の伝統そのものが西洋化されると考えた円了の説明を以下に記す。
(32)
この中で円了は、明治時代において様々な面での変化が起こる際に生じる、日本人の精神の変化について解説している。彼によれば、宗教が持つ固有の性質を国家発展の基盤に加えれば、変化していく状況の中で、不変の精神の一脈を連続して持ち続ける事ができ、離散紛失を免れる事が出来るという。この事から、これまでのように愛国の思想を人民の心中に保持させたいのなら、宗教を維持する事が最善なのであるとすすめている。続いて、日本の政治や法律その他あらゆる事が変化し、またその変化がさらに続いていく時代であるので、尚のこと宗教を維持してこれまでの精神を保続しなければならないという。もしこれをせずに外教を導入すると、日本人の精神は西洋化し、最終的に日本人の精神を全て忘れる恐れがあると警告している。
続いて円了は、ほとんどの日本人は愚民であるので、外教が導入されると日本人の特性がなくなり、日本社会が西洋化されるようになると考察している。
円了は、世界中のどの国においても、多数の人民は無智で愚民であるが、愚民の思考を押さえつけるためには宗教より良い方法がないと主張している。昔から政治家はこの観点から政治と宗教との関係の基盤を築いてきた。近代時代になっても、日本人の多数は愚民であり、神仏二教の信者においても愚民が多数であると論じている。そのため、愚民の不平を直し、彼らに満足を与え、政治に対する暴行暴動を防ぐには、「訓導するの良法は、旧来の宗教を特待するより外なし。これを特待するときは、これと同時にその僧侶および頑愚の信徒に満足を与うることを得べし。」と提示している。しかし、円了は、日本の旧来の宗教を圧状させるため外国の宗教の力を借りて普及するように援助する計画を立てる政治家の試みを懸念している。これらの試みが実施される時に、「僧侶の不平とともに愚民の不平を促し、愚民の暴行暴動を誘うに至るは必然なり。たとえその暴行暴動は直接即時に発せざるも、もしその内心に抱きたる不満不平、他の政治上の不和争乱に乗じて一時に発するに至らば、その害いうべからず。」と警告している。そのため、円了は日本社会の安定を保つため、日本の旧来の宗教に相当の保護を政治上において与えることが必然であると強調している。
4-2.円了が考える宗教の独立
円了は、外国の宗教はその由来の国に属するものなので、日本の宗教とは全く異なり、優先の基準に拠って特待法を変更すべきであると、以下のように述べている。
(33)
このように、円了は日本に導入され存在している諸外教は、種々雑多の宗教と宗派があるが、これらはまだ外国の教会と連携するという課題を残している。ここで円了が挙げている例は、ロシア、イギリス、フランス、アメリカの教会である。日本でのロシアの教会はまだロシアに属し、フランスの教会はまだその本国の支局であり、イギリスの教会はその本国の教会と関係し、アメリカの教会はその本国の教会と連携しているという。また、日本でのこれらの教会では、外国の宣教師が説教と宗教活動を行い、属する国から扶助金を仰いでいると説明している。円了は、これらの宗教には様々な宗名や主義、儀式、会堂の建築法、堂内の装飾などがあるが、「みなその外国にあるものの写真にして、一毛一点も異なることなし。はなはだしきに至りては、その説教の語声音調まで外国人の仮声をなすものあり。」と批判している。そのため、これらの宗教は外国の宗教と名称すべきであり、日本の宗教というべきではないと主張している。一方、日本の歴史上の国体と皇室を支えてきた神仏二教は、これらこそ日本の宗教であるので、外国の宗教と同様な待遇をされるべきではないと強調している。
また、円了は外教と外国政府との間に関係があることに関して以下のように懸念しながら警告している。
(34)
円了は、外国の宗教の中でもキリスト教を対象としている。彼によれば、キリスト教は日本の宗教ではなく外国の宗教であるので、日本に広まると同時に外国の政府の干渉が生じるという。例えば、日本にあるロシアやイギリスなどの教会は、属国の教会の分局出張であり、教会の費用は外国の教会より支出され、その宣教師は外国人であるので、その国の君主に従うこととなるという。結果として、その教会の信者となる日本人は、「暗にその入会の当日より外国の主君を奉戴するを義とするものなり。もしこれを奉戴するに至らざるも、その本国を思い、その本国を尊ぶの心長ずるは必然なり。」と警告している。円了によれば、外国の教会のこうした宗教的な属性は、日本人が日本国家を思い尊び、愛国する心が次第に減少していくと懸念している。
続いて、外国と密接な関係を持ったままの外教が日本に導入される際の問題点と文化上の影響について解説している。円了によれば、外国の宗教は本国の風俗や、習慣、礼式、交際等が混入しているという。そのため、外国の宗教が日本に入ると、その国の国風や民情などが同時に日本に入ることとなると説明している。ここで、円了は西洋諸国の例を挙げている。西洋諸国はそれぞれの国固有の趣があり、例えばイギリスの国風はフランスと異なり、ドイツの国風はロシアと異なっている。要するに、これらの国々の宗教と同時に各国固有の特性が日本に入る時は、日本独自の風土と人民独立の思想が失われることは必然であると警告している。例えば、イギリスの国風が日本に入る際には、日本の国風が支配され、またアメリカの民情が日本に入れば日本の民情が支配されることによって、将来日本国家と日本人の独立がなくなると懸念している。
4-3.円了が考える危険とその警告
円了は、日本の従来の宗教と外国の宗教との間にある、多様な性質や組織、主義などの面における相違について以下のように論じている。
(35)
彼によれば、外国の宗教においては宗派が異なることによってその主義が異なるため、各派間に不和が起きるという。一方、こうした不和は日本の旧来の宗教と宗派間には起きないと比較している。また、外国では多数人民が信仰し、その国体と民俗に適合する宗派は政府に待遇され、国家の公認教となるので、宗教間また宗派間信者を増やし待遇される争いが生じるという。円了の考えでは、こうした不和を抱える外教の各宗派が日本に導入されると、信仰に対する日本人民の間に競争が激しくなり、将来この不和を押さえることができなくなり、その影響は国家独立上に及ぶこともあると警告している。ここで円了は、日本政府にこうした困難的問題が生じる前に、予防の方法を考えて設けるべきであると主張している。
次に、円了は日本に外国の宗教が導入される際に、どのような恐れを考えているかを見てみよう。円了が外教を恐れる理由は、キリスト教だからではなく、単に外国から由来された宗教だからでもないという。外教を恐れるか恐れないかということは、次の諸条件を考慮に入れて定めるべきであると考えている。ここで円了は、日本に外教が導入されると生じる八つの恐れを指摘している。第一は、日本がその外国より強く、日本文明の進歩がその国を超える時に、外国から宗教が導入されることには恐れがないということである。第二は、その外国が日本と同盟親睦の国であり、いかなる事変があっても日本の敵にならない場合は、その国から宗教を導入する恐れがない。第三は、その外国の政体と国風が日本と同一の場合は、その国から宗教が導入されても恐れがない。第四は、キリスト教は日本の旧来宗教と同一し、調和することになれば恐れがない。第五は、その外国に日本人と同様な知識と学問があり、万国の事情に通じ、愛国の精神に富むのであれば恐れがない。第六は、外国と全く関係がなく、日本の国体や民俗などに適する一種の別離のキリスト教を構造するのであれば恐れがない。第七は、外国から日本に一度導入されて害があったが、日本の国力でその宗教を撲滅し禁止することを得られるのであれば恐れがないと提示している。第八は、日本の政治や法律、その他一般の制度の基礎が定まっている際は、宗教の一部分に変化があっても国家全体には影響を及ぼすことがないので、恐れることはないと主張している。
結論
以上で触れたように、円了は日本の伝統を守るため、様々な理由を語りながら旧来の宗教とりわけ仏教を保護すべきであると強調しているが、彼が上述した理由を踏まえたうえで以下の点を指摘したい。
まず、筆者は円了が仏教と日本の皇室との間に歴史的縁故があり、日本国家の基盤であったという発言に対し疑問がある。ここで円了は、イギリスの歴史にて縁故があるキリスト教の例を挙げながら、日本の状況を実証しようとしている。円了は、イギリスでは国家が形成された過程において、古来の縁故、いわゆるキリスト教が最重要な土台の一つであったという。日本の場合は、旧来の宗教と比べたら国皇室国体の永続を保護してきたのは仏教であると主張している。故に、歴史的な縁故の深い宗教である仏教を守り、「その宗教を特待せざるべからず」と説き、続いて「少しわが国に縁故なき宗教と同一視するの理あらんや」と指摘している。言い換えれば、円了は日本史にて日本国家を支えて、「もって国家鎮護の一助となしたるがごときは、名実ともに仏教をもって国教に組織したるものなり。」と考えている(36)。
歴史的背景で触れたように、仏教に対する新政府の軽視やキリスト教の布教と伝道などにより打撃を受けてきている仏教を救おうとする円了の意図が把握できるだろう。しかし、円了は日本史における日本国家と仏教の歴史的な縁故についての主張が漠然であるうえ、政権と対立した仏教の様々な事件について一切述べていない。彼が形容している仏教は、日本国に歴史的に深い関係があり国家体制を支える平和な宗教と集団である。だが、歴史を振り返ってみると実際上の出来事は異なっており、円了が語っているような平和的な関係ではなかった時期もある。平安時代には荘園制度により有力寺院は独自の土地を持ち、それを基に豊富な財力を蓄え、市町で町商人に対する独自の税を徴収し、独自の軍隊、所謂僧兵を作っていたという事件を否定することはできない。また、戦国時代にて天台宗や日蓮宗などは弱小な戦国大名より力を持ち、宗派間での紛争が起こったことも有名である。その中で武装した僧兵を抱えた仏教の宗派は軍閥したり、武力で他宗派の中小寺院を恫喝したり、上納金を納めさせて事実上幕府と共に支配している。例えば、戦国時代の京都における天文年間に起きた宗教一揆や松本問答、天文法難などの歴史的事実がある。
円了は、仏教とかかわった上述の事件(事実)を考慮せず、欧米諸国で多くの争いを起こす外国(欧米諸国)の宗教と異なり、日本では仏教によって生じる争いや競争がないと主張している。繰り返すことになるが、実際に歴史を振り返ると、織田信長による比叡山焼き討ちや一向宗焼き討ちなどの事件もある。こうした仏教と政治体制との争いが信長や秀吉、家康によって続き、江戸時代になると武力的な争いは漸くなくなった。だが、伝道的な面においても仏教宗派の中での衝突は起きており、日蓮宗は法華経のみが信者を救う唯一の教えであるという過激的な態度を貫いたことも見逃すことができない。筆者は、円了が主張する、仏教が日本の政教分離を支える平和な宗教であることには正当性・実証性がないと考えている。
また、次に指摘したい点は円了の用語についてである。円了は、歴史的事実と相違しつつ、日本の宗教間、とりわけ仏教を形容する際に競争といった穏やかな言語を採択している。一方、外国の宗教、とりわけキリスト教について説明する場合には争乱や熾烈な競争といった物騒な単語をあえて選択している。言い換えれば、円了は、あえて激しい単語を用いることにより外国の宗教が採用されると起こりうる弊害を、日本人の深層心理に植え付けるために強く主張することによって、仏教が平安であることを際立たせることに努めていると言えよう。
また筆者は、円了における仏教と日本の伝統と文化の結びつきにも無理な説得があると見える。彼は「かつ中古わが国の文学は全く仏教によりて成り、その時代の著書一として仏教の主義に出でざるはなし。その他、当時の美術、遊興、風俗、礼式、みな仏意に基づきて組織したるものなり。」と主張しているが、その信ぴょう性と正確性には疑問が残る。その中で、円了が述べる「文学」や「著書」、風俗、美術などは「みんな仏意に基づ」いていることは必ずしもすべてが間違っているわけではないが、大げさな表現であると言えよう。例えば、日本の最古の歴史書、また文学的な価値がある『古事記』は、神典の一つとして神道を中心に日本の精神或いは宗教文化に多大な影響を与えているものである。
最後に指摘したい点は、日本社会における宗教の役目についてである。まず、宗教家である円了はリベラル主義者である福澤諭吉と異ならず、上目の視線で一般の日本人を見て、民衆を抑える手段として宗教を利用することをすすめている。しかし、円了と福澤が考える、国家の建設における宗教の役割はかなり異なっている。福澤は、「宗教を拡て政治上に及ぼし、以て一国独立の基を立てんとするの説は、考の条理を誤るものと云うべし。」と述べている。それは、宗教というのは一個人の私徳に関係する事であって、建国独立の精神とは考え方が違っている。そのため、宗教で人心を維持したとしても、その人民と共に国を守るような事態が起こった時にはそれ程大きな功能があるわけないだろうと論じている(37)。一方、円了は福澤と異なり、日本の愚民の不平を直し、政治上害を起こさず暴行暴動を防ぐために、「訓導するの良法は、旧来の宗教を特待するより外なし。これを特待するときは、これと同時にその僧侶および頑愚の信徒に満足を与うることを得べし。」と提示している。彼の考えでは、日本政府は政治社会の安定を支える仏教を利用しながら、保護し特待した方がよいと考えている。
「3-2.円了における宗教と政体」で触れたように、欧米諸国で公認教とされている宗教は同国の政体に最も適切なものであるという条件が考慮されているという。共和政体に基づくアメリカの宗教は君主国である日本に不適切であると主張している。筆者は、円了の理論には実証性がないと考えている。彼は、アメリカの宗教の組織は「自由」や「平等」などを重んじるので、日本の政体上の思想に適切ではないと決めつけている。だが、円了は「自由」や「平等」に基づくアメリカの宗教とは何かについて述べていない。また、明治時代の知識人は「自由」や「平等」など西洋文明の価値観に対して肯定的なり又は否定的なりの態度を示していたのに対して、円了はこうした近代的価値観についてはっきりした態度を見せていない。言い換えれば、円了はこうした価値観に対して少なくとも肯定ではなかったといえる。
筆者は、明治14年政変の流れを通して円了を含む多くの知識人の見解が把握できると考えている。まだ全国的な支配を得ていたわけではなかった明治政府は一般民衆の人心をコントロールすることによって一日も早く全国的支配権を確立することが必要であった。明治政府は天皇が神であり、最高の指導者であることに反対する論者を苦しめつつ、広く一般民衆に認識させようと努力していた。それによって新政権の正統性を保障し、権威づけるとともに、天皇を民族的統一と国家的統合の機幅としようとしたのである。また、明治政府は、天皇巡幸を通して天皇崇拝を民衆に広め、全国に新しくおこってきた対立勢力『民権派』に対抗し、自由民権運動を克服して天皇制国家を確立しようとしたのである(38)。こうした時代の流れの中で、円了だけではなく多くの知識人が「自由」などの西洋文明の価値観に関する議論を避け、明治政府の方針の支えとなることも多かった。例えば、福澤諭吉は明治14年政変以降の執筆書を見ると、明治政権の方針に片寄り、「親敵」と形容してきた儒学を慶應義塾のカリキュラムに導入した。一方円了は、明治政権に仏教を公認教と認めてもらうため、同政権に沿うような態度をとっていたことは想像に難くない。
明治時代では、学問の自由がうたわれる状況の中で様々な思想があったが、円了を含む明治時代の知識人には類似点があった。それは、国民意識を形成する必要があるという認識を抱いていた点である。明治時代においては、政府と国民は日本が植民地化されるという共通の危惧があり、宗教家からリベラル主義者までの第一の本願は、日本の近代国家を建設することであった。そして、各主義者(思想家)は、自分の思想を生かすことを第二の目的にしていたようである。こうした課題を詳細に検討・考察することは、日本の近代化の過程をさらに深く理解することができると考えており、今後の研究課題にしていきたい。
注
1.「The Religious Influence of Buddhism as an Obstacle to the Reception of the Gospel in Japan
(日本において、キリスト教への信仰をはばむ仏教の宗教的な影響力) 」
2.小野尚香、「資料・抄訳:日本において,キリスト教への信仰をはばむ仏教の宗教的な
影響力」『佛教大学総合研究所紀要』2008年03月PP.93
3.上掲書 P.94
4. 西嶋和夫、「日本仏教と明治維新」『印度學佛教學研究』 46(2), PP. 821-826, 1998年、
P.824
5.「神仏判然令」太政官達第196号・1868年3 月。しかし翌月の4 月には「神仏分離実
施を慎重にすべき令」太政官仰226号の通達が出る。『明治以後宗教関係法令類纂』p.
737
6.小野田俊蔵、「明治時代の仏教僧が推進した仏教教育制度の改革」『佛教大学宗教文
化ミュージアム』PP.1-8、2016年3月、P.1; (村田安穂「明治維新廃仏毀釈の地方的展
開とその特質について」池田英俊編『論集日本仏教史─明治時代』vol.8、雄山閣、1987
年、pp.69-87)
7.1877年に内務省は社寺局を設けて仏教諸宗派の宗制等を各管長に委ねた。そのころか
ら宗としての意識を持ち本格的に教団が意識されるのは教導職の廃止(1884年8 月の太
政官布達第19号) 後であると考えられている。
8.東西本願寺は戊辰戦争に直面した明治政府に各々三万両を超す資金提供を申し出た。
また、西本願寺は北海道の開拓にも多くの資金を提供したと伝えられている。
9.「明治時代の仏教僧が推進した仏教教育制度の改革」P.1
10.上掲書 PP.2-3
11.上掲書 P.3
12.井上円了『真理金針初編』明治文化研究会編『明治文化全集』第十九巻、日本評論社、
1967年。芹川博通「明治中期の排耶論─井上円了を中心として─」『論集日本仏教史8
明治時代』池田英俊編、雄山閣出版、1987年、pp. 163-188
13.「明治時代の仏教僧が推進した仏教教育制度の改革」P.3; (三宅守常「仏教の世俗倫
理への対応─井上円了の修身教会設立をめぐって─」『論集日本仏教史8 明治時代』池
田英俊編、雄山閣出版、1987年、pp. 289-308)
14. オリオン・クラウタウ、「明治中期における日本仏教の言説的位相―仏教公 認運動
を中心に―」『宗教研究』 85(4), 2012年3月、P154
15.上掲書 P.154
16.谷川穣、「明治中期における仏教者と俗人の教育」『人文学報』第94号PP.37-76、京
都大学人文科学研究所2007年2月
17.上掲書 P.37
18.上掲書 p.37
19.上掲書 P.28
20.井上円了、『日本の政教論』P.5-7
21.上掲書 P.5
22.上掲書 P.6
23.上掲書 P.6
24.上掲書 P.7
25.上掲書 P.7
26.上掲書 PP.7-8
27.上掲書 P.8
28.上掲書 PP.8-9
29.上掲書 P.10
30.上掲書 P.11
31.上掲書 PP.15-6
32.上掲書 PP.11-2
33.上掲書 PP.12-3
34.上掲書 PP.13-5
35.上掲書 PP.16-8
36.上掲書 PP.6
37. 福澤諭吉、『文明論之概略. 巻之六』、[福澤諭吉]著者蔵版 1875年、P.33
38. 奥村淳、「明治14年明治天皇庄内巡幸」『山形大学人文学部研究年報』 (5) PP.59-100、 2008年2月、P.59
参考文献
高橋昌郎、『日本歴史全集 15 近代国家への道』、講談社 1969年
沼田次郎、『日本歴史全集 17 開国前後』、講談社 1969年
弓削達、『岩波講座日本歴史7 中世 1 』、岩波書店 1974年